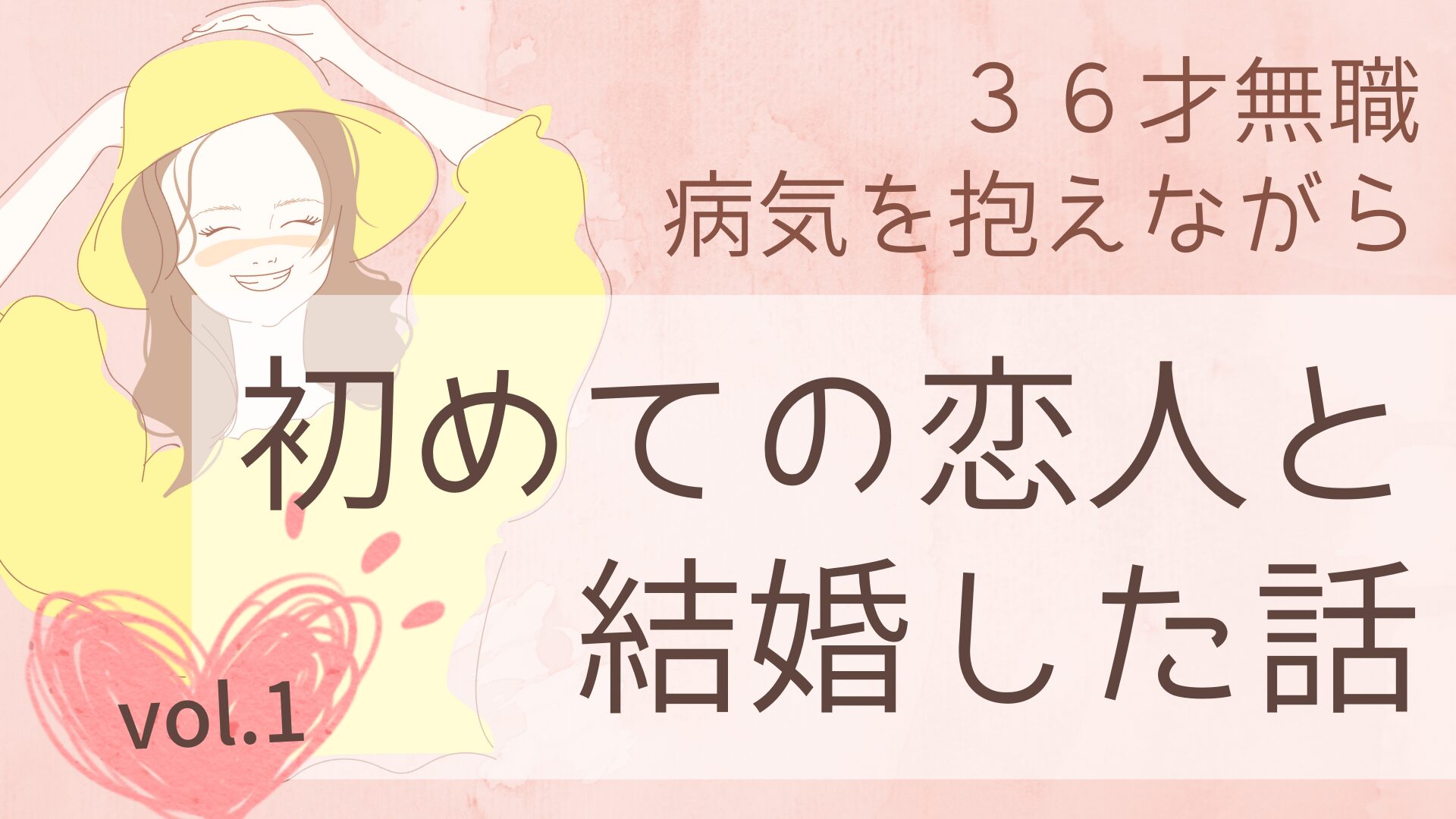恋人いない歴=年齢の36才、無職、病気。
いろいろ抱えながら、たくさんの思いを経験をしながら、初めての恋人と結婚した私のストーリーをエッセイ風にして連載にしました。
プロローグ
子供の頃から私には恋愛がよくわからなかった。
なぜ世の中には恋愛の歌が多いのか。
なぜ恋愛がテーマのドラマや映画が多いのか。
なぜ年頃になるとみんなイキイキと恋の話に花を咲かせるのか。
恋ってそんなに楽しいものなのだろうか。
他のことよりも夢中になれるものなのだろうか。
人を本気で好きになるってどんな気持ち?
本気で愛されるのってどんな気持ち?
私がその答えを知ったのはずっとずっと後の話。
恋愛は私の世界にはない別の世界のおとぎ話
私が子供の頃に求めていたもの。
可愛さよりカッコよさ。柔らかさより強さ。しなやかさより強靭さ。
少女漫画より少年漫画。ドキドキのときめきより心が燃えるような熱い展開。
真っ黒になるくらい外で体を動かして遊ぶのが好きで、やせて小柄で活発な女の子だった。
そのくせシャイで注目を浴びるのは大の苦手。
目立ちたくなくて水泳の選抜選手を決めるリレーではわざと遅く泳いでいたり、うっかり選抜に選ばれたときなんかは胃が痛くなるほどストレスを感じていた。
女の子はとってもませているものだ。
小学生の頃から毎日恋のうわさでもちきりだった。
○○くんが△△ちゃんのこと好きなんだって。
私実はね、□□くんとそのお兄ちゃんも好きなんだ~
今の見た?2人絶対両思いだよね!
私もこういう話は嫌いでも苦手でもなく、年相応に興味はあった。
だけど恋が自分の世界に入ってくることなんて想像できなくて、違う世界の話を聞いているようだった。
そんなことよりも宇宙に思いを馳せたり、ゲームや漫画の世界を生きる方が何倍もワクワクした。
だけど周りはそうではなかった。
あるとき同級生の男の子から告白された。
好きです!と叫んでどこかへ消えていった。
取り残された私は、私が校舎裏に呼び出されたことに色めき立つ同級生の好奇の目のさらされ、恥ずかしくていたたまれなくなった。
仲の良いおせっかいな女の子がいろいろと心配してくる中、私はもうその場から立ち去り全てをなかったことにしたかった。
イレギュラーを嫌う私は、心を乱すできごとを運んできた彼に対して怒りさえ覚えた。
私の世界にこんなことが起こるなんて。
あの子が私のことを好きだったなんて。
全部が想定外。
その後私も彼も何事もなかったかのように友達を続けていたが、彼は一体どんな気持ちで私と話していたのだろう…

変わってみたいけど刺激と変化は怖い
中学の時期の大きな変化と言えば初潮。
初潮を迎えてから男性を恋愛対象として少しづつ意識し始めていた。
周りの同級生たちも大人へと近づいていき、恋の話もますます娯楽として盛んになっていた。
そんな中私は夢を見ていた。
私好みのカッコいい男性が私と恋に落ちるのだ。
偶然バス停やお店で何度も出会い、楽しい会話を重ねていく。
その男性は私より年上で大人びている。
私を優しく、時にはちょっと強引にリードしてくれて、私がとても大切で貴重な宝物であるかのように感じさせてくれるのだ。
私の頭の中の王子さまは、いつも現実世界より甘くて優しい。
想像力のたくましい夢見る少女は妄想の世界に浸っていた。
そんな妄想少女にも現実で好きな人ができた。
陰からこっそり眺め、彼がこっちを見ていない時だけじっと熱い視線を送る。
目が合ったらすかさず逸らし、気付かれていないかな?見すぎちゃったかなと心配になる。
運よく会話できたときなんて天にも昇る気持ちだった。
好きな人と話すときは自分が自分ではなくなってしまうようだ。
うまく自分をコントロールできなくて、想像していたストーリーとはまるで違う退屈な展開になってしまう。
でもそれでよかった。
好きな人がいる、それだけで私の生活には華やかな色どりが加わり、明るい音楽が流れ始める。
ほんの少しだけ、みんなが恋愛に夢中になる気持ちがわかった気がした。
だけど私の心はちょっとした挨拶と想像だけでお腹いっぱいになってしまい、それ以上の刺激は歓迎していなかった。
あるとき家に誰か訪ねてきた。
幼馴染の男の子だった。
妙にソワソワしていて、私もつられてソワソワしてしまう。
彼は話を切り出した。
〇〇(私の名前)のこと好きだから付き合わん?
予想していた通りの話だった。
学校でも近所でもあまり接触がない上に、夜にわざわざ訪ねてくる理由なんてそのくらいしか思いつかない。
付き合ってくださいなら分かるけど、付き合わん?ってなんなんだとぼんやり考えていた。
いいよ。
私はなぜか承諾していた。
わかりやすく喜んで走り去る彼を見送りながら、親に尋ねられたらなんて説明しようと考えていた。
恋人がいることが一つのステータスとなりうる思春期の頃。
そんな時に告白されて、相手を好きでもないのに承諾してしまったことへの罪悪感に苛まれた。
友だちの距離感から恋人の距離感へと変わっていくこと、私の世界に彼が入ってくることに対して強い抵抗を感じた。
あれは自分が変わってしまうことへの抵抗だったのか、未知のものに対する不安だったのか。
ドキドキ震えながら彼の家に電話し、彼にやっぱり付き合えないと伝えた。
悲しんだかな、悲しまないわけないよね。傷ついたよね。自分の未熟さを心底憎んだ。
内側へ、そのまた奥へと潜っていく
高校に進学してからの私は本の虫だった。
想像の中で生き、目の前の人間や学校には興味が持てなかった。
そんなふうだから私は周りから浮いていた。
表面上は何となく友達。私には人に心を開く意思がないことを周りも察知したのだろう。
だってわからないんだもの。どうやって心を開けばよかったの?
心の開き方を習っていない。
集団生活は大嫌い。よりどころのない孤独な学校生活にだんだんと心は蝕まれ病んでいった。
頭の中は常に暗く、出口のない長い長いトンネルにいるようだった。
恋のときめきの魔法も効かない。
漫画や小説のワクワクも効かない。
私の世界からは色がなくなったようだ。
もし心を病む前に、大好きな人から求められ、愛され、不安も恐れもその愛で包み込んでもらうことができていたなら。
私も愛する人を癒し、支え合い、お互いがオアシスのような存在になれていたとしたら。
物語の展開は変わっていたのだろうか。
ますます私は自分の世界に入り込むようになっていった。
外の世界に心を開くことを極端に恐れていた。
初めの頃は何となくいいなと思える人もいたけれど、私にとって恋愛はもはやファンタジーと同じ。
存在してはいるけれど、私がその小説の中を生きることはできない。
夢見ていたバラ色生活は叶うことなく、高校生活は終わりを告げた。
なんてことはない。これまでと同じなだけだ。